どうも、怒りん坊パパです。
さて、四谷大塚の4年生の勉強について、算数、社会、国語と紹介してきました。
最後は、理科になります。
理科は、娘っ子も息っ子も比較的得意科目でしたが、全科目/全期間を通じて、最低偏差値(25台)と最高偏差値(70以上)をたたき出した!?のは、2人とも理科です。
偏差値の差はおよそ50近くあり、正直、一喜一憂します。
そんなジェットコースターな科目!!「理科」の勉強法の紹介です。
四谷大塚の理科のカリキュラム
理科も社会と同様、身近な疑問の「なぜ?」をもとに、各分野の興味を引き出す展開をしています。
「いろいろな昆虫」から始まり、「鏡と光の進み方」、「磁石」、「太陽や月の動き」、「水の変化」、「春の頃、夏の頃」など、ほぼ4分野万遍なく網羅されています。
4年生のうちは、結構、「へぇー」ってな感じで、割と楽しい感じで学べると思います。
1週間の勉強サイクル
理科の1週間の勉強サイクルは、割とシンプルです。
4年生では、社会同様、復習が中心のため、予習は、「予習シリーズの音読」と「予習ナビ」をやり、あとの問題演習等は、授業後の復習として取り組むよう、指導されました。
1.予習シリーズ読み
予習シリーズを読みます。
塾からは、「音読するように」と言われるのですが、息っ子は、音読より黙読の方が頭に入りやすかったです。音読か、黙読は、頭に入る方でよいと思います。
2.演習問題集-まとめてみよう
4年生では、「まとめてみよう」をやるのですが、「予習シリーズ読み」の後、続けてやるのではなく、他の科目の勉強をやって時間をおいてからの方が、定着度を確認する上でよいと思います。
3.予習ナビ
予習ナビですが、時間に余裕がなければ割愛でもいいと思います。もしくは、わからない単元だけみるようにするなど、その時の内容によって決めて良いと思います。
※視聴は1.5倍速で見るのをオススメします。(速い速度で見ると、脳の処理能力が上がる!と何かで読んだのと、時間の短縮になります)
4.塾
とにかく、集中して、先生の話を聞くようにさせました。理科は他の科目より、疑問が湧くことが多いので、積極的に先生に質問できるようになると、しめたものです。
5.塾の解き直し
塾で小テストなどがあったときは、その解き直しを翌日には真っ先にやりました。
6.要点チェック
点検の意味も込めて、授業後に要点チェックをやりました。
7.演習問題集
練習問題を解きます。○つけを忘れずにやりましょう。
中学受験の理科に役立った参考書、問題集
正直、役立つ参考書、問題集は数多くあると思いますが、全てはできないと思います。基本は、塾に高い月謝を払っているので、塾を主軸にし、参考書利用は目的をはっきりさせ、選ぶのがいいと思います。
とはいえ、子供に「あう/あわない」はあると思うので、ある程度試行錯誤して、買ったりして使わないのも出てきますが。。。
「受験理科の裏ワザテクニック」シリーズ
理科は、予習シリーズと演習問題集で理解を進めるのは問題ないと思っていましたが、4年の後半から5年一杯、分野によって理解できないものや、問題を解く上でわからなくなるものが、ところどころ出てきました。
そんなとき、先生に聞いたりもするのですが、予習シリーズで本文を読んだり、演習問題集を解いたりしてわからなかったら、他の観点からの理解を深めるために「受験理科の裏ワザテクニック」の該当箇所を読ませていました。
裏ワザテクニックというだけあって、テクニック的なことが書いてあります。
「解き方がわからない」、「覚え方がわからない」といったときに予習シリーズとは違ったやり方や語呂合わせなどで習得できます。
この裏ワザテクニックシリーズですが、3冊に分かれています。
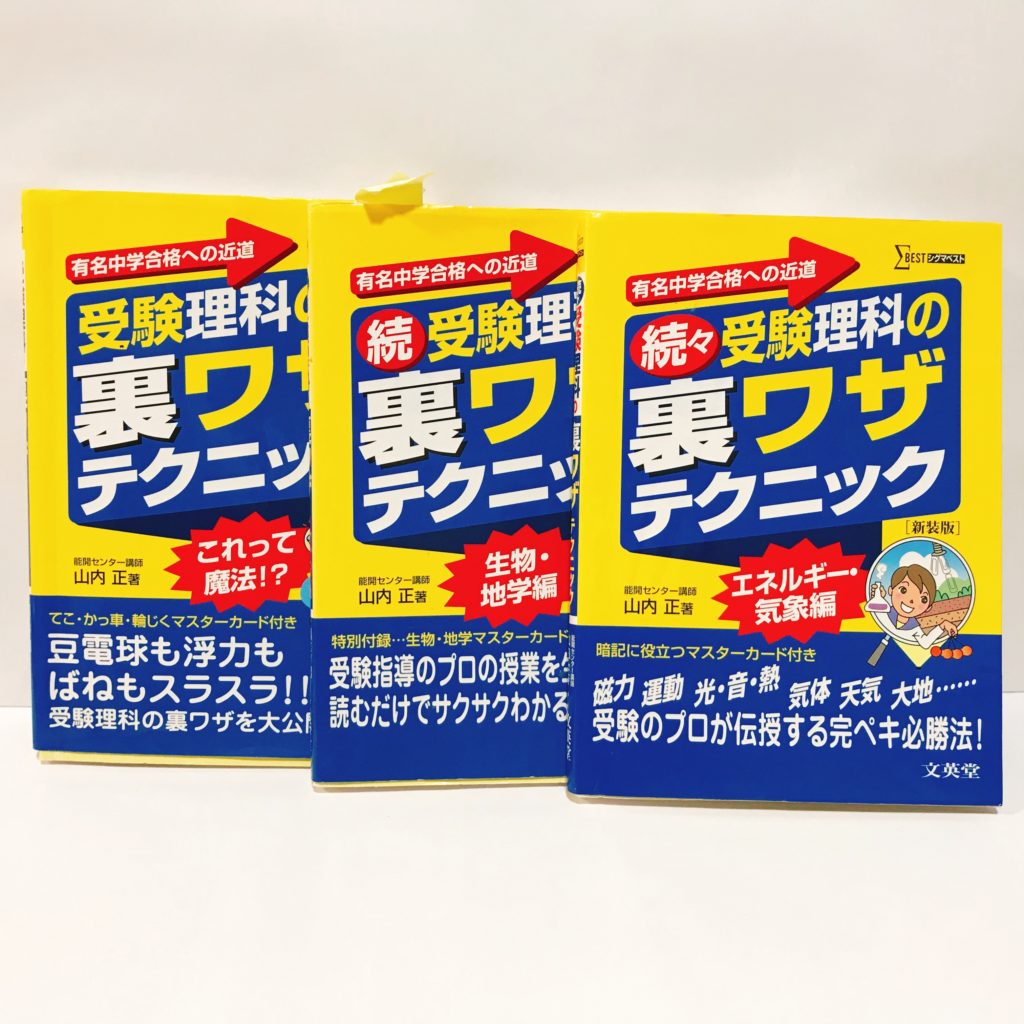
内容的には、単元の最初に単元で必要な内容の説明をStep別にわかりやすく書いてあり、ときに例題を交えながら、最後に確認チェックで各単元のポイントをチェックするといった流れです。
また、「てこ」のような難易度に幅がある単元では、標準版、難関版と分けて説明があり、実力に応じた構成もみられます。
算数も3冊持っていますが、算数、理科ともに結構、面積図を使って解く方法がでてきます。
頭から読むというより、予習シリーズや演習問題集でイマイチよくわからない時に該当の単元を読んだり、解いたりするのが我が家での使い方でした。
予習シリーズの音読するときに併せて読むのもアリかと思います。
3冊のそれぞれの構成ですが、こんな感じです。
我が家は、3冊一気に買いました。
1.「受験理科の裏ワザテクニック」
豆電球と乾電池、浮力、ばね、てこ、かっ車、輪じく、化学反応比、中和体積比、よう解度と比、実験器具2.「続 受験理科の裏ワザテクニック」
月、太陽、星、金星、消化と吸収、血液循環、セキツイ動物のなかま分け、こん虫、魚の育ち方、植物3.「続々 受験理科の裏ワザテクニック」
文英堂 「受験理科の裏ワザテクニック(続、続々含む)」より
磁界、モノの動き、気体、音、光、熱と物質のすがた、気象観測、天気の変化、人の誕生、大地のでき方、環境問題
苦手な分野だけを利用するのもありですね。
メモリーチェック理科
言わずと知れた日能研のメモリーチェックです。
四谷大塚の「四科のまとめ」に相当するものと思われますが、こちらの方がよりコンパクトにまとまっています。
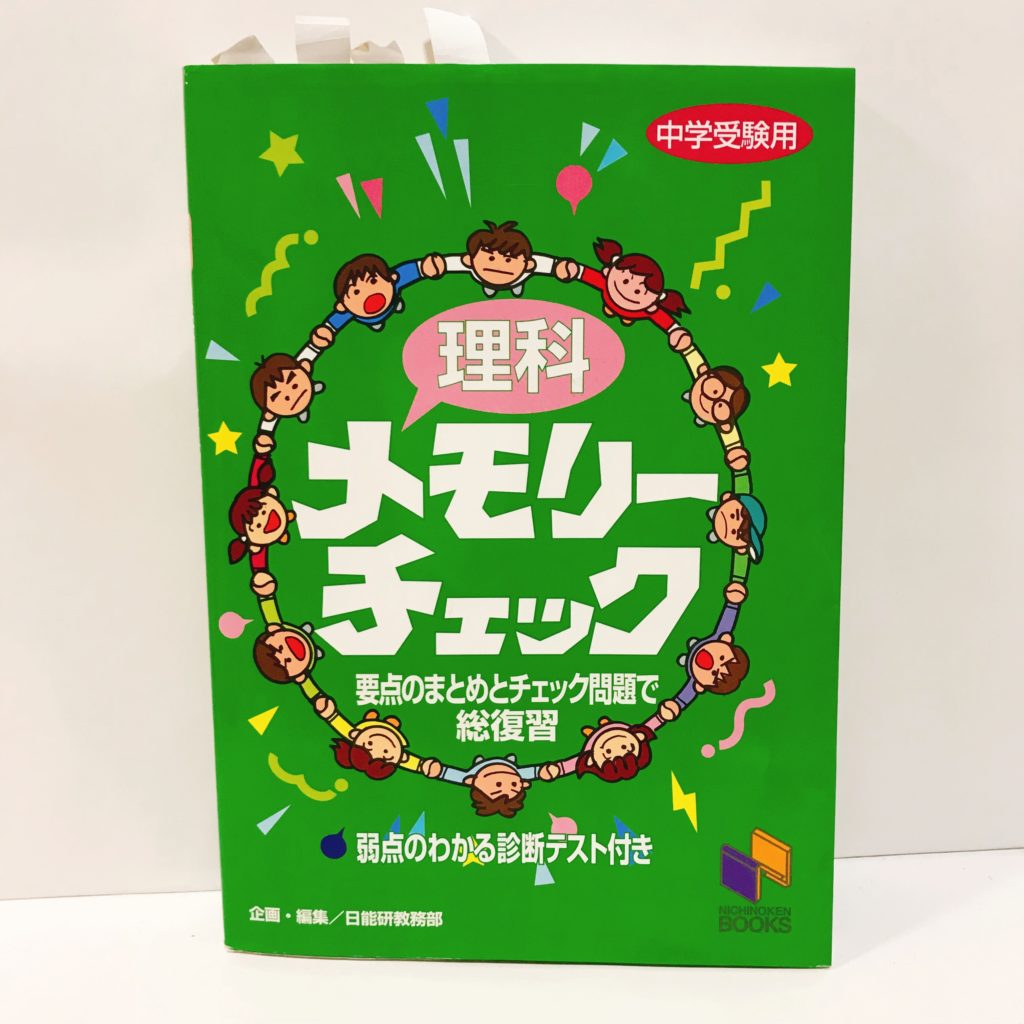
内容的には、メモリーチェックという名前の通り、覚えておくべき「要点のまとめ」が、見開き左ページに簡潔にまとめられており、右ページには、「ポイント・チェック問題」が掲載されています。
「四科のまとめ」は、比較的記述問題も多いのですが、「メモリチェック」は、主に受験で必要となる知識系がまとめられており、チェック問題もほぼ短答式です。
4年生は、単元毎の復習、振り返りをする際、「要点のまとめ」が見易くて重宝していました。
時間があれば、1週間のサイクルの「7.演習問題集」のところで、「ポイント・チェック問題」に取り組むのがいいと思いますが、我が家は時間がなく、組分けテスト前に苦手そうなところを解いていました。
5年生では、組分けテスト前に該当範囲の週テストで、成績が良くなかった単元を中心に問題を解き、5年後半では、巻頭の「弱点診断テスト」で弱点部分の洗い出し、補完をしていました。
総合理科表 e-サイエンス
こちらは、早稲アカのNN麻布で配布された冊子になります。
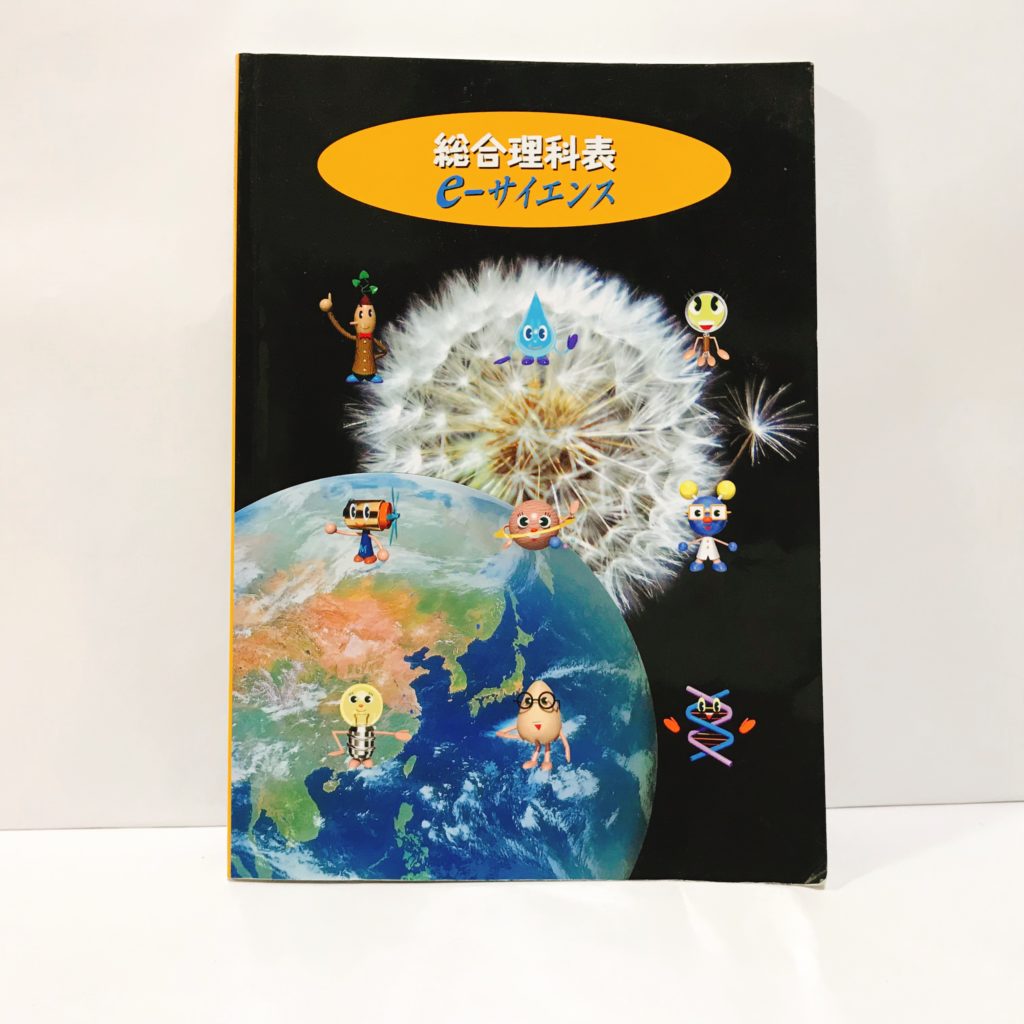
見開き2ページ分で1テーマを扱っています。もちろん、知識系もありますが、仕組み系、実験系が多い感じです。
例えば、「電子レンジでなぜ温まるのか?」とか、「環八雲のでき方」など、豆知識的なところから始まり、仕組みを理解できるようになっています。
テーマ系の出題がある学校については、これと「子供の科学」を読んでおきたいところです。
息っ子が塾の行き帰りで読んだり、息抜きに拾い読みしていました。

これは面白い!大事に中学校でも使うつもり。
まとめ
理科は、生物、地学、科学、物理と4分野あり、苦手と得意な分野が共存する不思議な科目で、苦手分野が出ると、撃沈しがちです。
娘っ子は、生物系(特に植物)が苦手で、息っ子は、地学系(特に天体)が苦手でした。
ただ、入試自体は、ほぼ4分野を均等に出題する学校が多く、1単元でのテストのような大失敗をすることは少ないとは思います。(ちなみに冒頭での偏差値25台は、分野別の週テスト、偏差値70台は、合不合判定や組分けテストなど範囲が広目のテストです)
もし、大外しをするとしたら、計算を含む誘導問題で最初で間違い、あとの問題が全滅パターンで大問1問分失点という感じしょうか。
以下の記事でもご紹介しましたが、理科は好奇心が大きくモノをいう科目です。
子供の好奇心を伸ばす声かけができるといいですね。
↓少しでもお役に立てていましたら、ポチッとお願いします。次を書く燃料補給になります!




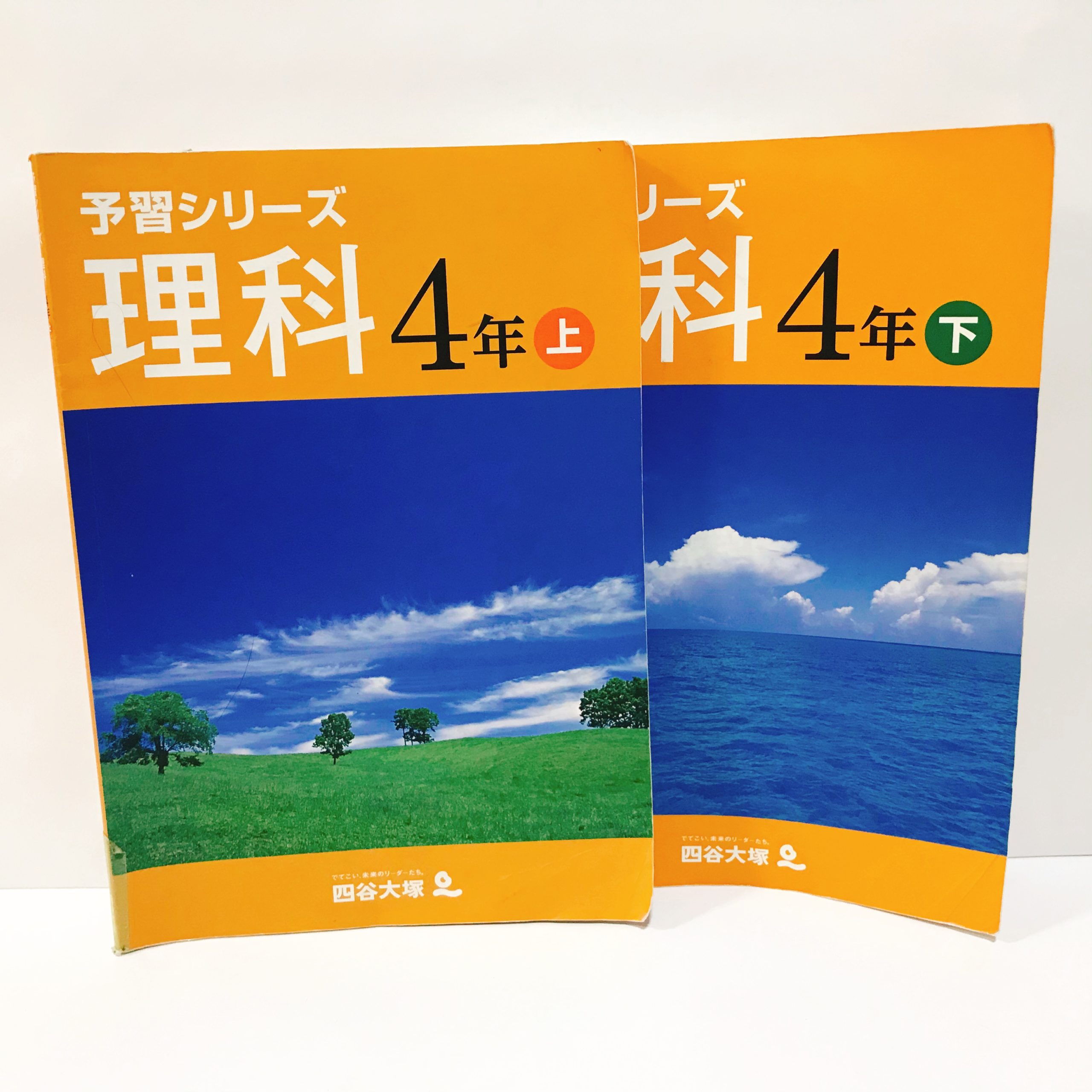




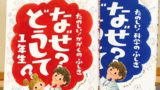
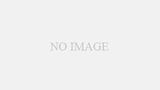
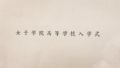
コメント