どうも、怒りん坊パパです。
毎年、6月に算数オリンピックがあります。
我が家では、四谷大塚の校舎からのお便りに算数オリンピックの申込の案内が書いてあり、四谷大塚の自校舎で、申込み、受験できました。
ちなみに娘っ子は参加せず、息っ子は5年生から参加しました。
今回は、算数オリンピックについて、お話ししてみたいと思います。
算数オリンピックとは?
算数オリンピックとは、小学生から中学生を対象とした、「算数、数学」のイベントで、5種目に分かれています。
- キッズBEE:小学1年生~小学3年生
- ジュニア算数オリンピック:小学5年生以下
- 算数オリンピック:小学6年生以下
- ジュニア広中杯:中学1年生~2年生
- 広中杯:中学3年生
5月中旬くらいまでに申込して、6月にトライアル、7月に決勝大会、8月に表彰式があります。
(公式HPは、「算数オリンピック」)
問題の難易度は、「オリンピック」というだけあって難しく、御三家レベル(ファイナルはそれ以上)だと思います。
息っ子は、5年生で「ジュニア算数オリンピック」、6年生で「算数オリンピック」に参加しました。
参加した時の様子は、こちらになります↓

算数オリンピックに参加すると、何がいいの?
算数オリンピックに参加すると、何がいいのでしょう?
メリット1:難問への免疫力がつく!
入試問題でこれ以上の難問(特にファイナル)は出題されないため、どんな問題に出会っても、
「算数オリンピックの問題ほど難しくはない!」
と難しい問題に対して、免疫ができます。
メリット2:類題が出題されるかも!?
入試問題で、算数オリンピックの問題と同じような問題が出題されるかも!?
息っ子の場合、麻布の模試ですが、同じ問題が出題されたことがありました。
メリット3:じっくり取り組む姿勢が身につく!
難問に対して、あきらめずにじっくり取り組む姿勢が身に付きます。
これは、御三家クラスを目指すお子さんは、5年生のときに身につけておくべきことだと思っています。
これが身についているか否かで、6年後半(過去問取り組む時期)に大きく差が出ます。6年後半で伸び悩む(合不合判定テストでは良い点を取れるが、過去問でなかなかいい点が取れない)のは、この取り組みが十分でなかったことが考えられます。
メリット4:捨て問を見分ける力
正答率0%という問題もあるため、問題を読んである程度、捨て問(難易度の高い問題)を見分ける力がつく。これも6年後半の得点力に結びつきます。

わからなくても、難しい問題に取り組むのが楽しかったなぁ。
算数オリンピックの対策、取り組み
我が家の場合、「参加した時の様子」の中でも書きましたが、パパと息っ子でお風呂で過去問に取り組みました。
なかなか難しいので、最初のうちは、取り組む問題を正答率をみて選ぶのがよいと思います。
トライアル問題で正答率が高いものから、徐々に難しい問題へ取り組み、2日、3日かけて、2人で(ときには、娘っ子も入れて3人で)
「あーでもない、こーでもない」
とやりました。

1人で考えるより、パパやお姉ちゃんの意見も聞くと、いろんな考えが浮かんだなぁ。
場合によっては、親が答えをみて、少しずつヒントを与えるのもいいかもしれません。(が、答えを読んでもよくわからんものもありました)
結局、算数オリンピックは参加した方がよい?
5年生のジュニア算数オリンピックをオススメします!
理由は2つあります。
1つは、6年生だと、やはり、スケジュールがタイトになったり、やることが山ほどあったり、また、開成を目指すお子さんの場合、開成本番レベルテストという後期の学校別対策コースの資格審査の試験とバッティングすることもあるからです。
2つめは、5年生のうちに「じっくり取り組む姿勢」、「思考力」を身につけておくのを断然、オススメします。(「メリット3」です)
普段の塾の勉強で考えると、応用演習問題集に辿りつけているのが一つの目安かもしれません。
さいごに
息っ子の場合、算数オリンピックを受けるとき、組分けテストや開成本番レベルテスト、日曜授業などとバッティングしました。
自校舎で受験できるので、ある程度は校舎長等に相談して、調整してくれます。小学生のときにしか参加できないものなので、可能であれば、参加してみるといい思い出になり、受験にもプラスに働くと思います。
↓少しでもお役に立てていましたら、ポチッとお願いします。次を書く燃料補給になります!







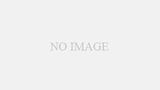
コメント