どうも、怒りん坊パパです。
四谷大塚の4年生の国語は、説明文と物語文を通して、文章の構造やテーマや要点・要約、場面や心情、主題などを学び、勉強習慣を身に付けます。
もちろん、それらの基礎となる語彙力、漢字力も身につけていかなければなりません。
今回は、そんな4年生の国語の勉強方法について、我が家のケースをご紹介したいと思います。
四谷大塚の国語のカリキュラム
四谷大塚の4年生の国語ですが、メインは、説明文と物語文で、あと、詩も少し入ってきます。
知識要素としては、「4年上」で漢字がメインで、「4年下」では、文法、慣用句/ことわざが中心となります。
4年生の文章は、比較的平易なものなので、授業についていけなくなることはないと思われますが、やはり、得意不得意があり、我が家の場合は、娘っ子、息っ子ともに国語は得意ではなく、テストの結果はあまりいいとは言えませんでした。
1週間の勉強サイクル
基本的に、予習は、文章を音読し、意味調べをすることと、漢字・知識を自習しておくことで、復習は漢字と知識の小テストで間違えた箇所の解き直しでした。
1.予習シリーズ-本文音読と意味調べ
予習シリーズの問題の本文を音読します。
あと、わからない言葉の意味調べをしておきます。問題については、授業で初見で触れて欲しいとの方針のため、解かずに授業に臨みました。
2.予習シリーズ-知識問題
予習シリーズの後半にある知識の説明を読んだ後、問題を解きます。
目標時間が記載されているので、時間を測って取り組みました。
3.漢字とことば
授業の中で小テストがあるので、その準備として取り組んでいました。クラスによって、合格点があり、合格点以下の場合、間違えた漢字を何回か書いて提出することになっていました。
4.要約
勉強のペースがつかめてきた生徒は、予習シリーズの問題の本文の要約を提出し、先生に添削してもらっていました。(が、我が家が取り組めたのは5年生からでした)
5.塾
解答解説にある解答用紙を切り取って、授業中に初見で答えを書き込み、添削してもらったり、自分で板書を書き込んだりしていました。
6.間違えた問題の解き直し
授業中に解いた問題を家で解き直しをして、提出する。(のが良いとされていましたが、我が家はたどり着きませんでした)
7.国語力5000
毎日コツコツやっていきました。
正直、娘っ子も息っ子も最後の方は、イヤイヤやってました。。。
8.日々のコラム
これも毎日コツコツやりました。
国語が苦手か、そうでないかが何で決まるのかは、受験が終わった今でもよくわかっていません。
娘っ子は、女子学院で致命傷にならないだけの国語の実力をなんとか身に付け、息っ子に関しては、麻布と志望校の国語に対しては、割と仕上がったと思います。
4年生で取り組んだ問題集
4年生で、思ったより国語の伸びがなかったため、主に2つの問題集に取り組みました。
出口の小学国語
我が家では、4年生の勉強に慣れてきた頃にこの本を娘っ子、息っ子ともに読ませて、やらせました。
出口の小学国語の一番易しい問題集になります。

この本の一番いいところは、国語という科目が「感覚の科目」ではなく、「論理の科目」であることを分からせてくれるところです。
また、説明文、物語文、随筆文などの解き方が記載されていて、それぞれの文章がどのようなものか、文種によって、何に気をつけて、どう解くかをさらっと一通り学ぶことができます。
1冊終えるのに、それほど時間はかかりませんので、勉強習慣が身についてきた頃の祝日や休暇中にやるのをオススメします。
ただ、一度やって終わりにしてしまうと、これらのエッセンスを忘れてしまうので、ときどき、読み返すようにした方がいいと思います。
ふくしま式「本当の国語力」シリーズ
続いて、ふくしま式です。
「偏差値20アップは当たり前!」とありますが、最初の持ち偏差値によるかと。。。我が家はさすがにそこまではいきませんでしたが、効果はありました!!
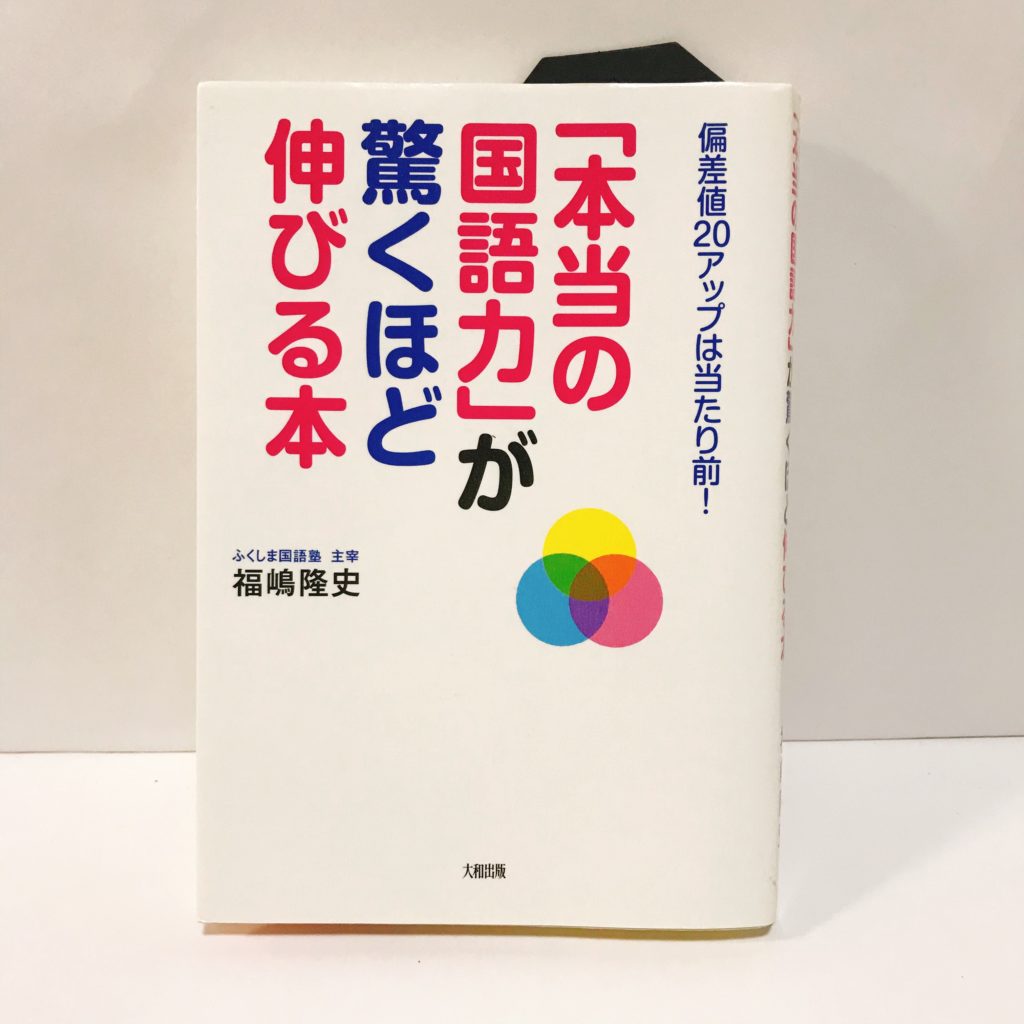
「『本当の国語力』が驚くほど伸びる本」は、親向けの本です。
「国語力とは?」とか、「国語力を伸ばしていく道筋」が書いてあります。
私も、「ふむふむ」と読み進め、一通り読んだ後、本の中に書いてある問題を口頭で、子供たちに出題し、答えを書かせたりしていました。
この本を親が読んでから、次の問題集をやらせるか判断するのがよいと思います。
次は、「『本当の国語力』が身につく問題集」です。
国語の力を大きく3つ「言いかえる力」、「くらべる力」、「たどる力」に分けて、小学生低学年もできる内容の問題から始まり、徐々にレベルアップしながら、力をつけていきます。
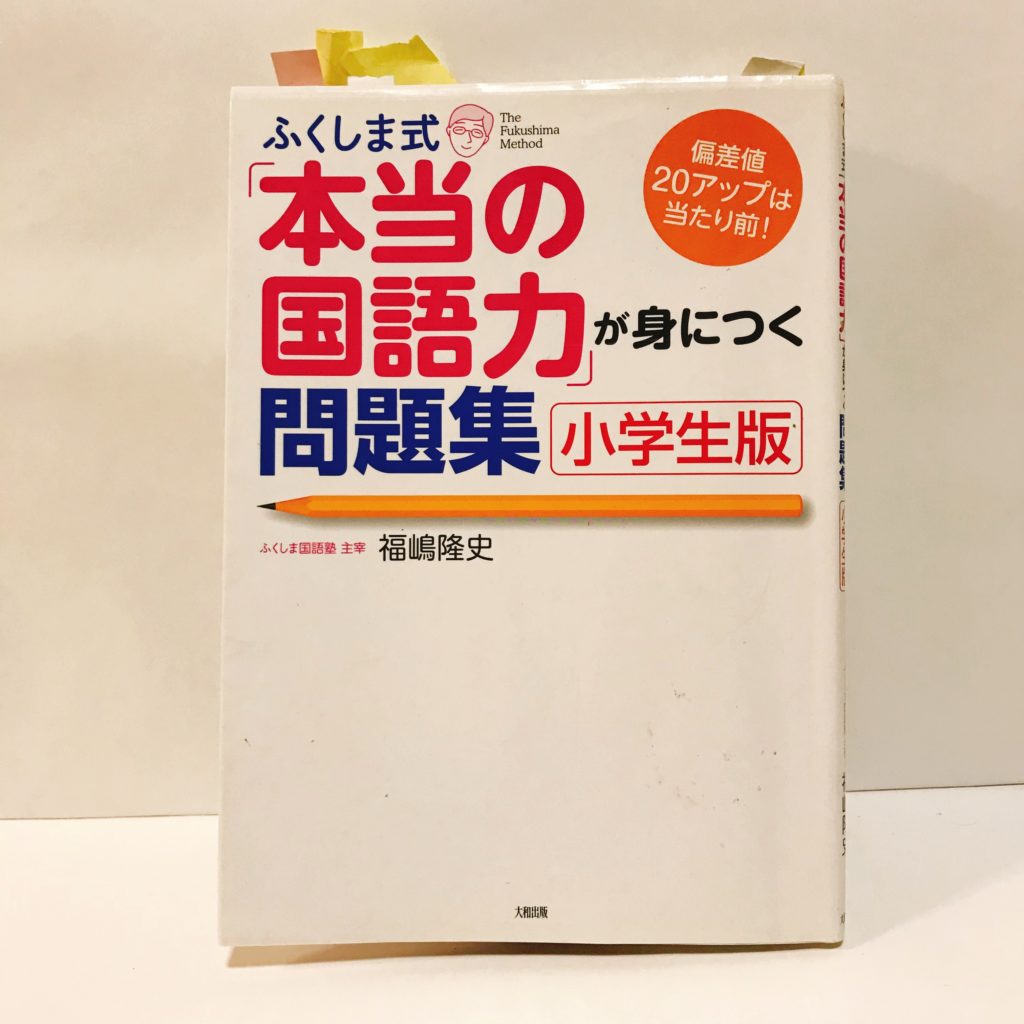
この問題集のいいところは、「自由に短作文を書きなさい」という問題があり、その答えとして、著者の塾の生徒さん(小学生~高校生)のさまざまな解答が載っており、それらに対し、評定がされている点です。
短作文の答えは1つではないですが、いろいろな答えがある中でも、評価のポイントが解説されていると、子供にとっても納得感があります。
こちらは、比較的書く練習が多く、文章の型を覚え、記述の基礎を固めるのに特に効果があります。主語、述語のちぐはぐな文章を書いているようなお子さん(我が家の場合、息っ子)に最適です。
また、見開きページが1つの学習単位になっているので、取り組みやすいのですが、全体としては、それなりのボリュームがあり、短期間では終わらないため、じっくり、コツコツと力をつけていく感じです。
我が家では、4年の後半から塾のない日で、時間の余裕があるときに1日1パート~2パートくらいずつ地道に取り組んでいきました。
まとめ
4年生は、勉強習慣を身に付けるのと、土台を作る時期です。
そのため、塾の学習がメインになりますが、今ひとつ国語の勉強というのがわからなかったり、リズムにのれない場合は、上記のような、少し予習シリーズと違う観点の問題集から、国語という科目を学ぶのもよいと思います。
その他では、4年生までに学習ではなかなか身につきにくい、心情などに触れる機会を増やすのがいいかと思います。
我が家は、娘っ子も息っ子も心情把握が苦手でした。
今考えると、4年生までの間に読書か、もしくは、テレビドラマなどをみながら、家族で、
「これは、やせ我慢の笑顔だね~」
とか、
「この怒った仕草は照れ隠しだね~」
とか言いながら、心情描写について、子供ともっと会話していれば、物語文が得意になったかも!?と思います。
国語は勉強の結果が現れるまで時間がかかり、かつ、対策の効果が見えにくいのですが、
「最近、国語で大ハズしをしなくなったなぁ」
と思ったら、効果の現れの1つだと思います。
辛抱強く、取り組みましょう!
ちなみに5年生のときに国語のテストで、記述が空白で点数が悪かった時の対策は、以下の記事で!
↓少しでもお役に立てていましたら、ポチッとお願いします。次を書く燃料補給になります!




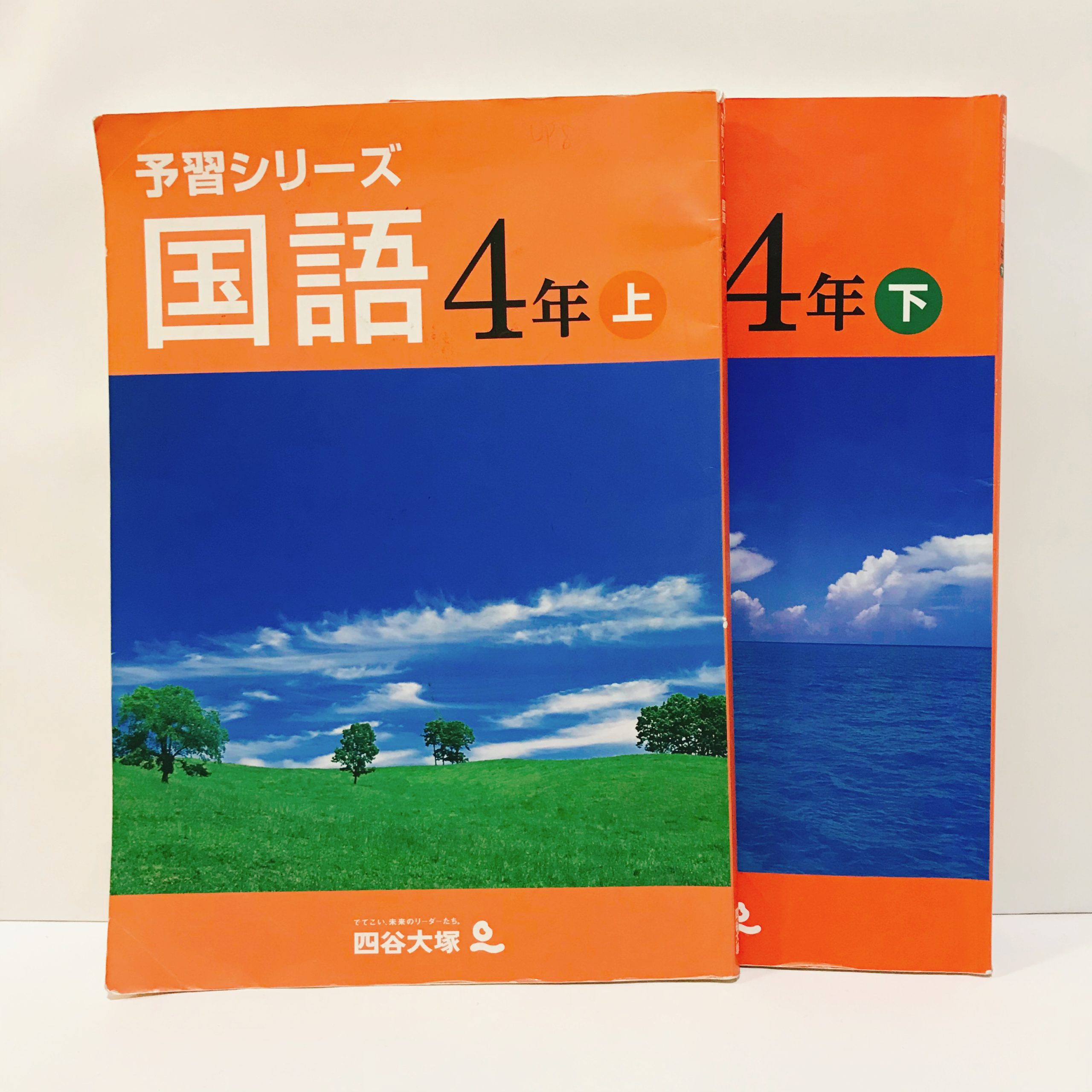




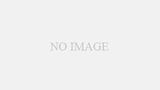
コメント